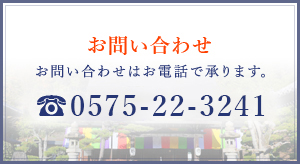先日ホームセンターに行きまして、ふらりと園芸コーナーを巡っておりますと、腰の高さほどある鉢植えのカンノンチクにふと目が止まりました。手のひらを目一杯広げたような細長い葉、真緑が鮮やかなカンノンチクを眺めていると… 遠い記憶が呼び起こされたんですね。
以前、当院の境内には先代住職が手を掛けていた鉢植えのカンノンチクが幾鉢かあり、園芸好きの檀家さんと先代がカンノンチク談議に花を咲かせていた光景を思い出したんですね。そんなこともあって久しぶりに観たカンノンチクに何やら心を惹かれて少し調べてみることにしました。
カンノンチクとは小型のヤシ科植物で、中国南部の原産であり、日本には江戸時代に琉球を経由して渡来し、古典園芸植物として栽培されるようになったとあります。さらに本種は園芸品種が多いことでも知られ、葉に斑が入るもの、葉が変形しているものなど、その特徴から〈達磨〉〈天山〉〈福寿〉〈小判〉など多くの品種が栽培されているそうです。さまざまな品種を収集して観賞できることは魅力的かもしれませんね。
もう一つ意外な特徴がありました。カンノンチクの花はとても珍しく、数十年に一度しか咲かないと言われています。花はクリーム色からピンク色をしており、珊瑚のような姿をしているとのこと。そういえばかつて境内にあったカンノンチクも花が咲いたことは一度としてありませんでした。人生に一度めぐり逢うカンノンチクの花、これも魅力の一つといえそうです。
そして何より、カンノンチクという名前が素晴らしいですね。観音竹と書きます。江戸時代に中国から渡来した際、沖縄県の首里にある観音堂という寺院でこの植物が栽培されていたことに由来して『カンノンチク(観音竹)』と名付けられたそうですね。仏教とのご縁をもったこの植物に尚のこと親近感を覚えるものであります。
かつてカンノンチクが境内にあった理由が、今ようやくわかった気がします。