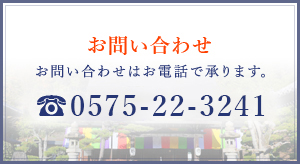2025年8月15日、戦後80年という節目の終戦記念日をまもなく迎えます。それは日本人であるならば「戦争と平和」について何かしらの思いを表すべき日でもあります。
毎年8月15日の終戦記念日を迎えるたびに連想するものがあります。それは『日本のいちばん長い日』という一冊の本。題名のとおり1945年8月15日、運命の一日を描いたノンフィクション書籍ですね。そして続けて連想するのがこの本の著者である故人、半藤一利さんです。
半藤一利さんといえば日本のジャーナリスト、元〈文藝春秋〉編集長、戦史研究家、そして自称「歴史探偵」でもあります。この「歴史探偵」という肩書きこそが、もっとも半藤さんの仕事ぶりを穿っており、なおかつ半藤さんの魅力を表しているともいえます。
大学教授や歴史学者など職業的な歴史家にとって「歴史」とは「資料に残った証拠」であることに対して、「資料を読んで歴史が分かったつもりになってはいけない」というのが歴史探偵・半藤さんです。「たくさんの資料を読み比べて、それらのあいだに何があるか、隠されたものはないかを考える、そうした思考からしか歴史的真実というものは浮かび上がってこない」とも語られています。
昭和5年東京生まれの半藤さんは昭和20年3月の東京大空襲で被災して九死に一生を得る体験をされています。そのときの様子を著書『B面昭和史』の中で、
「辛うじて生き延びたわたくしが、この朝に、ほんとうに数限りなく眼にしたのは〈人間ですらない〉ものであった。たしかにゴロゴロ転がっているのは炭化して真っ黒になった物。人間の尊厳とかいう綺麗事はどこにもなかった。戦争というものの恐ろしさの本質はそこにある。非人間的になっていることにぜんぜん気付かない」
と書かれています。
これほどの戦争体験をされて、二度と悲惨な戦争を繰り返してはいけないと『日本のいちばん長い日』『昭和史』といった歴史学者では到底踏み込めないであろう真実の歴史に迫った歴史探偵・半藤一利さん。戦後80年の現在においては半藤さんほどの非戦の「語り部」が現れることはもはやあり得ません。
しかしながら幸いにも多くの著作を残されています。折にふれて半藤一利さんの本を繰り返し読んでみる。平和を願う私たちがこの先できることの一つでもあります。