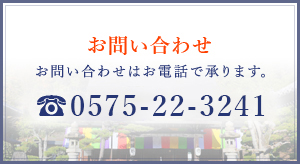私たち浄土真宗のご信徒の方は他の宗派と違い少し苦労をされますね。「信仰は浄土真宗です」と自己紹介したあとに、相手から「どちらですか?」と質問されることが多く「お東です」あるいは「お西です」と付け加えなければなりません。多くはこれで会話は終わりますが、さらに相手から「お東とお西は何が違うんですか?」と問われることがあるやもしれません。今回は「お東とお西」の違いについて取り上げてみることにします。まずは概要から、
「お東」とは〈真宗大谷派〉のことを言う通称ですね。ご本山は正式には〈真宗本廟〉、通称が〈東本願寺〉であります。
「お西」とは〈浄土真宗本願寺派〉の通称であり、ご本山は〈龍谷山本願寺〉、通称〈西本願寺〉となります。
具体的に比べていきますと、まずご本尊の形が違います。大谷派(東)の阿弥陀さまの立像には船後光がありませんが、本願寺派(西)の立像には後光の下に船後光という部分があります。またご本尊を掛け軸にした御画像の場合、後光の数が違います。大谷派の阿弥陀さまには6本、本願寺派の阿弥陀さまには8本となっています。
さらにお仏壇や仏具の違いがありますね。お仏壇の柱が黒塗りになっているのが大谷派で、柱が金箔で加工してあるのが本願寺派でもあります。それとは反対に花立、香炉、蝋燭立などの仏具は大谷派が金色の物を使用し、本願寺派は黒っぽい色合いの物を使用します。
他にもお焼香の回数、数珠の持ち方などにも違いがあるようです。しかしながらこうして比べてみると明らかに大きな違いといえるものは見受けられません。それもそのはずですね、遡ること500年前の戦国時代には浄土真宗はひとつでした。
歴史の教科書にも登場する織田信長の石山本願寺攻めを巡って分派することとなった大谷派と本願寺派は、江戸時代後半にはお互いが歩み寄り、現在では両者の関係はとても良好で東本願寺と西本願寺を含む真宗教団連合という組織で交流も深めています。
これも当然のことであります。「お西」も「お東」も宗祖 親鸞聖人のお教えを深く学び、お念仏に喜ばせていただくこと、なんら違うことはありません。