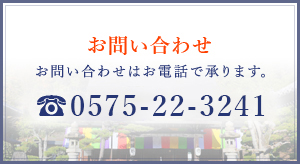横断歩道を渡る小学生が、一時停止している車のドライバーに向けてお辞儀をしてくれる場面があります。お辞儀を受けたドライバーは心が洗われる思いがして、これからも横断歩道の前では歩行者のために一時停止しようと心掛けるきっかけにもなる素晴らしい日本の慣習でもあります。
子供たちがしてくれた「お辞儀」とは挨拶や感謝、敬意などを表すために、相手に向かって腰を折り曲げる動作のことをいいますね。そしてお辞儀には種類があり「最敬礼」「敬礼」「会釈」と分けられるそうです。文字通り敬意を表すのが「敬礼」であれば、感謝を表すのは「会釈」ということになります。
この「会釈」という言葉を国語辞典で調べてみますと、『軽く一礼すること』『挨拶や礼を交わす所作』とあり、さらに『仏教語「和会通釈(わえつうしゃく)」の略語』と出てきます。私たちが日常的に使う「会釈」という言葉も仏教がルーツだったんですね。
仏教語である「和会通釈」とは、仏教経典の中の異なった説を相互に照合し、その真義を明らかにすることをいいます。この四字熟語が「会通」あるいは「会釈」と省略して用いられるようになり、表面上は互いに矛盾するものを調和して意義が通じるようにすること、さらに転じて、多方面に気を配り、相手の心を推しはかって応対すること、相手を思いやることを「会釈」といいます。そして今日ではそのような心遣いを身体的に表すお辞儀のことを「会釈」と呼ぶようになったんですね。
相手を思いやる「会釈」という言葉。横断歩道で子供たちから会釈されましたら、いうまでもなく会釈でお返しするべきですね。